2025-07-22、
Windows 10、11などから「Linux」に乗り変える時の具体的な方法と、Windowsと同じように使えるようにするためのコツは?
Windows 10/11からLinuxへの移行は、少し慣れが必要ですが、多くのメリットがあり、いかんせん無料で使える事でしょう。ここでは、具体的な移行方法と、Windowsと同じように使えるようにするためのコツを詳しく解説します。
1. なぜLinuxに移行するのか?
移行を考える前に、Linuxのメリットとデメリットを理解しておきましょう。
■メリット:
・軽量で高速 : 古いPCでも快適に動作することが多い。
・セキュリティが高い : ウイルスやマルウェアの標的になりにくい(Windowsに比べて)。
・カスタマイズ性が高い: デスクトップ環境からシステム設定まで、自由に変更できる。
・オープンソース : 無償で利用でき、コミュニティによるサポートが充実している。
・プライバシー : Microsoftによるデータ収集を気にせずに使える。
■デメリット:
・学習コスト : Windowsとは異なる操作方法やコマンドラインに慣れる必要がある。
・ソフトウェアの互換性: Windows専用ソフトがそのまま使えない場合がある(代替ソフトやWineなどの互換レイヤーで対応可能)。
・デバイスドライバ : 一部の特殊なハードウェアではドライバの導入が難しい場合がある。
・ゲーム : 最新のWindowsゲームはLinuxでは動作しない、またはパフォーマンスが低い場合がある(Protonなどの登場で改善されつつある)。
2. 移行の具体的な方法
大きく分けて3つの方法があります。
2.1. 仮想マシンで試す (おすすめ)
まず、既存のWindows環境に影響を与えずにLinuxを試す最も安全な方法です。
使用するツール:
・VirtualBox (無料)
既存のOS上で、別のOSを実行するのに使う仮想環境(仮想マシン)を構築するためのオープンソースソフトウェアです。Windows OS上で、Linux系OS(Cent OS・Ubuntuなど)を動作させることもできます。
・VMware Workstation Player (無料版あり) など
手順:
1)仮想マシンソフトウェアをWindowsにインストール。
2)LinuxディストリビューションのISOファイルをダウンロード (後述のおすすめを参照)。
3)仮想マシンソフトウェアで新しい仮想マシンを作成し、ダウンロードしたISOファイルを指定してLinuxをインストール。
■メリット:
WindowsとLinuxを同時に起動でき、気軽に試せる。問題が発生してもWindows環境に影響がない。
■デメリット:
物理PCに直接インストールするよりもパフォーマンスが落ちる場合がある。
2.2. デュアルブートで試す (中級者向け)
WindowsとLinuxを同じPCに共存させ、起動時にどちらのOSを使用するか選択する方法です。
手順:
1)Windowsのディスクパーティションを縮小し、Linux用の空き領域を作成。
2)LinuxディストリビューションのISOファイルをダウンロードし、USBメモリに書き込む (Rufusなどのツールを使用)。
3)USBメモリからPCを起動し、Linuxを空き領域にインストール。
4)起動時にOSを選択するメニューが表示されるようになる。
■メリット : 物理PCの性能を最大限に活かせる。
■デメリット: パーティション操作を誤るとWindowsが起動しなくなるリスクがある。
2.3. Windowsを完全に削除してLinuxをインストール (上級者向け/最終手段)
Windowsを完全に削除し、PC全体をLinux専用にする方法です。
手順: デュアルブートの3. と同じだが、インストール時にディスク全体をLinuxに割り当てる。
■メリット : 最もシンプルで、ディスク容量を効率的に使える。
■デメリット: Windowsに戻すのが大変になる。
3. おすすめのLinuxディストリビューション
Windowsからの移行者には、使いやすさやWindowsとの類似性から以下のディストリビューションがおすすめです。
1)Zorin OS:
特徴: Windowsのようなインターフェースを標準で提供し、Windowsからの移行者にとって最も親しみやすいデザイン。Wine(Windowsアプリ互換レイヤー)がプリインストールされており、Windowsアプリの動作も期待できる。
おすすめポイント: 見た目の親しみやすさ、初心者向けの配慮。
—関連記事—
・【特集】サポート切れの「Windows 10」のPCに「Linux」をインストールして使い続ける方法
2)Linux Mint (Cinnamonエディション):
特徴: Windows XPや7に似たデスクトップ環境を提供し、直感的に操作できる。豊富なソフトウェアが利用可能で、安定性も高い。
おすすめポイント: 安定性、使いやすさ、コミュニティの活発さ。
3)Ubuntu (GNOMEまたはKDE Plasmaエディション):
特徴: Linuxディストリビューションの中で最も有名で、情報が多く、困ったときに解決策を見つけやすい。GNOMEはモダンなデスクトップ、KDE PlasmaはWindowsに似たカスタマイズ性の高いデスクトップ。
おすすめポイント: 圧倒的な情報量、ソフトウェアの豊富さ、活発なコミュニティ。
4. Windowsと同じように使えるようにするためのコツ
LinuxはWindowsとは異なるOSですが、工夫次第でWindowsと同じような快適な環境を構築できます。
4.1. デスクトップ環境の選択とカスタマイズ
前述のおすすめディストリビューションは、Windowsライクなデスクトップ環境をデフォルトで持っているか、選択可能です。
・Zorin OS (Zorin Desktop): Windowsに近い見た目と操作感。
・Linux Mint (Cinnamon): Windows 7のようなスタートメニューやタスクバーが特徴。
・KDE Plasma (Kubuntuなど):
非常に高いカスタマイズ性があり、Windows XP/7のような見た目から、よりモダンなデザインまで自由自在に設定可能。
デスクトップのテーマ、アイコン、壁紙などを変更することで、より自分好みの見た目にできます。
4.2. ソフトウェアの代替と互換性
Windowsで使っていたソフトウェアと同じものがLinuxで使えるとは限りません。代替ソフトウェアを探すか、互換性レイヤーを利用します。
■オフィススイート:
・LibreOffice:
Microsoft Officeと高い互換性を持つ無料のオフィススイート。
Word, Excel, PowerPointに相当するWriter, Calc, Impressが含まれます。
・WPS Office:
Microsoft Officeに近いインターフェースと高い互換性を持つ無料のオフィススイート。 WPS Officeは、中国のKingsoftが開発した総合オフィスソフトウェアです。
・Microsoft Office (Web版):
ブラウザ経由で利用するWeb版のOfficeはLinuxでも問題なく利用できます。
■Webブラウザ:
・Google Chrome,
・Firefox,
・Microsoft Edge
など、主要なブラウザはLinux版が提供されています。
■画像編集:
・GIMP : Photoshopの代替となる高機能な画像編集ソフト。
・Inkscape: Adobe Illustratorの代替となるベクター画像編集ソフト。
■動画編集:
Kdenlive, Shotcut, DaVinci Resolve (無料版あり): 高機能な動画編集ソフト。
■チャット/コミュニケーション:
Discord, Slack, ZoomなどはLinux版が提供されています。
◼︎Windowsアプリケーションの実行 (Wine/Proton):
・Wine (Wine Is Not an Emulator):
WindowsアプリケーションをLinux上で動作させるための互換レイヤー。
すべてのWindowsアプリが動作するわけではありませんが、多くのアプリが動作します。
・Proton:
Steamが提供するWineベースの互換レイヤーで、SteamのWindowsゲームをLinuxで動作させるために使われます。これにより、多くのWindowsゲームがLinuxでもプレイ可能になっています。
・CrossOver (有料):
Wineをベースにした商用ソフトウェアで、Wineよりも手軽にWindowsアプリを動かせるように開発されています。
4.3. 日本語入力の設定
ほとんどのLinuxディストリビューションでは、インストール時に日本語が選択されていれば自動的に日本語入力環境が設定されます。もし設定されていなければ、以下の手順で設定できます (例: Mozcという日本語入力エンジンを使用)。
◼︎システム設定を開く:
(デスクトップ環境によって場所は異なりますが、「設定」や「地域と言語」などの項目を探します。)
◼︎地域と言語/入力ソース:
「入力ソース」または「キーボード」の項目で、日本語(Mozc)を追加します。
入力方式の切り替え:
通常、Ctrl+SpaceキーやWindowsキー+Spaceキーなどで切り替えが可能です。
4.4. ドライバのインストール
Linuxは多くのハードウェアドライバを標準でサポート(Linuxカーネルに入っています)していますが、一部のグラフィックカード (特にNVIDIA製は入っていない) やWi-Fiチップセットでは、追加のドライバが必要になる場合があります。
◼︎追加ドライバマネージャー:
多くのディストリビューションには、「追加ドライバ」や「プロプライエタリドライバ」といったツールが用意されており、自動的に必要なドライバを検出してインストールしてくれます。
◼︎各デバイスメーカーのサイト:
一部の周辺機器(プリンター、スキャナーなど)では、メーカーがLinux用ドライバを提供している場合があります。
■Linuxの場合は、Windowsとちょっと違うので、下記のようなサイトを読んでから、実施してください。
・Linuxでドライバーをインストールする正しい方法って何?
4.5. ファイル管理とネットワーク共有
■ファイルマネージャー:
Windowsのエクスプローラーに相当する「ファイル」(GNOME)や「Dolphin」(KDE Plasma)などがあり、直感的に操作できます。
■Windowsとのファイル共有:
SMB/CIFS: Windowsの共有フォルダにアクセスしたり、Linux側から共有フォルダを作成したりできます。ファイルマネージャーからネットワークドライブとして接続可能です。
■クラウドストレージ:
Google Drive, Dropbox, OneDriveなどのクラウドストレージサービスを利用すれば、WindowsとLinux間でファイルを簡単に同期できます。
■USBメモリ/外付けHDD:
FAT32やNTFS形式でフォーマットされていれば、WindowsとLinuxの両方で読み書きできます。
4.6. コマンドライン(ターミナル)への慣れ
WindowsでもコマンドプロンプトやPowerShellがありますが、Linuxではコマンドラインを多用することがあります。最初は抵抗があるかもしれませんが、少しずつ慣れていくと非常に強力なツールになります。
◼︎基本的なコマンド:
ls (ファイル一覧), cd (ディレクトリ移動), mkdir (ディレクトリ作成), rm (ファイル削除), sudo (管理者権限での実行) などから始めると良いでしょう。
◼︎パッケージ管理システム:
apt (Debian/Ubuntu系) や dnf (Fedora系) などを使って、ソフトウェアのインストールやアップデートを行います。
例: sudo apt update (パッケージリストの更新), sudo apt upgrade (パッケージのアップグレード), sudo apt install [ソフトウェア名] (ソフトウェアのインストール)
5. 移行をスムーズにするためのヒント
バックアップ:
移行前にWindowsの重要なデータを必ずバックアップしておきましょう。
■段階的に試す:
最初から完全に移行するのではなく、仮想マシンやデュアルブートでLinuxを試用し、慣れてから完全移行を検討するのが賢明です。
■情報を集める: 困ったことがあれば、Google検索で「[ディストリビューション名] [やりたいこと]」と検索すると、多くの情報が見つかります。日本語のコミュニティも活発です。
■楽しむ:
新しいOSを学ぶことは、新しいスキルを身につけることでもあります。楽しみながらLinuxの世界を探求してみてください。
WindowsからLinuxへの移行は、少しの努力で新しい可能性を広げることができます。ご自身のPCの使用目的や習熟度に合わせて、最適な移行方法とディストリビューションを選んでみてください。
——————————————————————————————

——————————————————————————————
・Linux標準教科書
「Linux標準教科書」は、初心者が基礎からLinuxを学ぶための学習用教材として、LPI-Japanが無料で公開しています。
——————————————————————————————
<追記1>
■大学生が開発したWindows 10→Linux移行ツール「Operese」が有望と話題、「Steam」ゲームを動かすデモも
<追記2>
■タダで「Windows 10」を1年間延命できる「ESU」の登録が開始されたので試してみました
—関連記事—
・エルピーアイジャパン(LPI-Japan)が、無償のLinux学習用教材「Linux標準教科書」の最新版Ver3.0.0を公開
・slax.orgが、USBメモリから起動できる軽量Linuxディストリビューション「Slax 9.3」をリリース
Sponsored Links
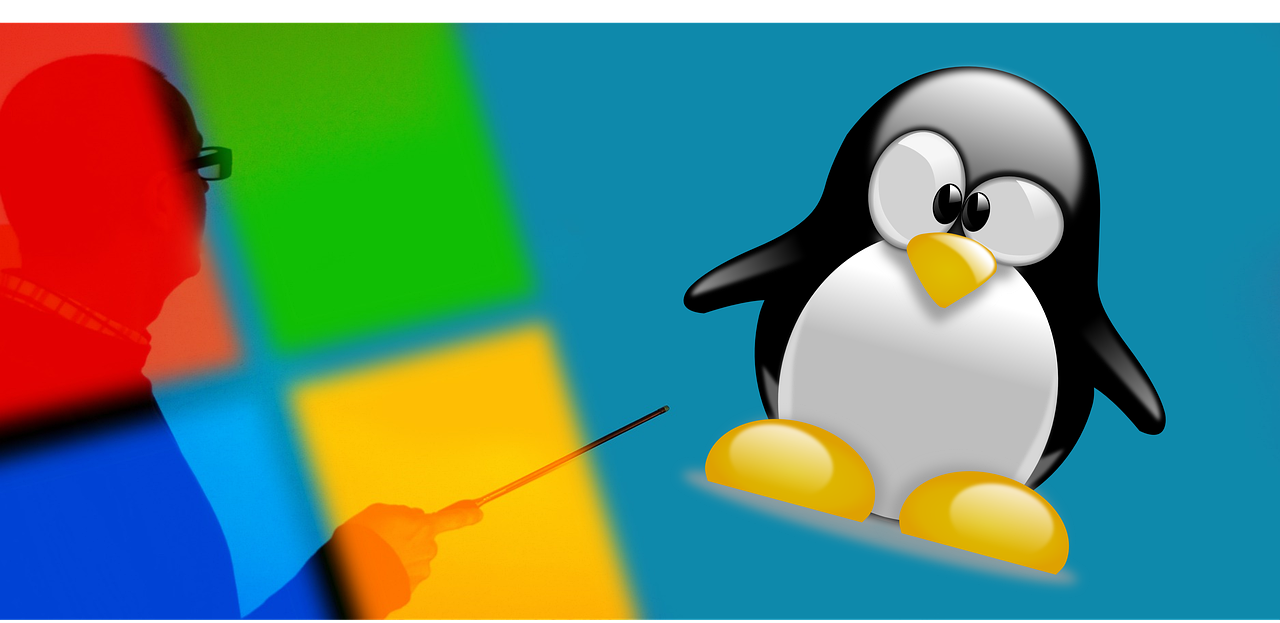






コメント